公的年金制度は社会経済情勢の変化に対応し発展してきた。
最近は人生100年時代の到来と共に老後の所得保障の中核をなす公的年金制度に対する期待と不安が入り交じって議論されるケースが増えている。そこで公的年金制度のこれまでと、現在、そして将来について見ることにする。
※本稿は2019年9月作成の内容となります。
我が国公的年金制度の歴史と発展
我が国の年金制度は今から144年前に海軍軍人への恩恵的な年金制度として明治8年に⎾海軍退隠令⏌がはじまりである。その後、官吏、教職員、警察官を対象に整備されていった。そして、大正12年には⎾恩給法⏌に統一された。
一方、民間の年金制度の始まりは昭和15年に、戦時体制下での船員の医療や労災保険も含む⎾船員保険法⏌の施行がはじまりである。
昭和17年には工場で働く男子労働者を対象に⎾労働者年金保険法⏌が施行された。
そして、昭和19年には適用範囲を男子事務員、女子労働者にも拡大し名称も⎾厚生年金保険法⏌に変更された。
その後急激なインフレにより制度の見直しが行われ、昭和29年に厚生年金保険制度の抜本的な改正を行い再スタートする。
昭和34年には無拠出の福祉年金制度が開始され、昭和36年には農業、漁業、自営業者を対象に国民年金制度が創設され、国民皆年金制度が発足する。
この頃までは公的年金制度の創設期であった。
したがって、この頃は一部の恩給受給者を除き現在のような年金額を受給する人はいなかった。一方、我が国は昭和30年代から40年代にかけて高度経済成長期を迎え、東京オリンピックの開催、いざなぎ景気、個人消費も旺盛で3C時代を謳歌する。
このような情勢の基で年金の給付水準の引上げの要請も高まり、昭和40年には1万円年金、昭和41年には厚生年金基金制度の導入、昭和44年には2万円年金、昭和48年には、5万円年金、物価スライド制の導入(現役時代の給料を現在価値に修正して年金額を計算する再評価制度)等の法律改正が行われ、まさに公的年金制度の発展充実期を迎える。
昭和50年代後半になると、我が国は諸外国にも例を見ないスピードで高齢化社会へと移行する。一方、産業構造、就業構造も変化してきた。このような社会経済の変化に対応し、年金制度を長期に亘り健全かつ安定的に運営していく必要性が出てきた。
すなわち、国民年金、厚生年金、各種共済年金等それぞれ分立した制度ではその運営基盤が不安定になる。一方、制度が分立していることにより、制度間の不均衡や過剰給付、重複給付等の調整が行われないと、長期的に安定した制度運営が行われないことも分かった。
このような状況の下、昭和60年改正が行われた。その主な内容は、全国民共通の⎾基礎年金制度⏌の創設と給付水準の適正化で、制度の成熟期に加入期間が40年に伸びることを想定し、年金額を計算する場合の給付単価、支給乗率を段階的に逓減することとなった。
その後、平成6年改正では、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を平成25年までに60歳から65へと引上げる。
平成12年改正では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ平成37年までに段階的に引き上げることとなった。
その他、厚生年金への加入年齢を65歳から70歳へ引き上げることも行われた。
そして、平成16年改正では、基礎年金の国庫負担割合を1/3から1/2へ引上げる。厚生年金の保険料率を平成16年から0.354%ずつ毎年引上げ、平成29年度以降は18.3%で固定する。
賃金の動向や労働人口等社会全体の保険料負担能力の変動に見合うよう年金改定率を調整するマクロ経済スライドの導入が行われた。
平成に入り年金受給者も増加の一途を辿ると共に加入期間の増加に伴い年金額も高くなっている。すなわち、公的年金制度にとっては成熟期を迎えている。
そして今後は少子高齢化がますます進行していく状況からマクロ経済スライドによる年金額の調整が行われるので、現役世代の手取り賃金に対する年金の水準は次第に低くなっていく状況である。
このように見てくると、現在の年金受給者は制度の上から見ると最も恵まれていると言える。昨今は、年金給付費の約7割は現役及び事業主の納めた保険料収入によって賄われている状況で、懸命に支えてくれている現役世代に感謝の気持ちを忘れてはならない。
公的年金・恩給を受給している高齢世帯の実態(2018年度調査結果から)
今回は実際に公的年金を受けている高齢者世帯の年金に対する意識調査から,年金の実態について見る。
厚生労働省は保健、医療、福祉、年金や所得等の国民生活の基本となる項目を調査し、厚生労働行政の企画や運営に必要な国民生活基礎調査を毎年実施している。
今回は2018年の調査結果が本年7月に公表されたので、その中から高齢者世帯(65歳以上の者のみか、65歳以上の者と18歳未満の者で構成)の公的年金に対する状況を見てみよう。
◇今回の調査では、高齢者世帯の一世帯当たりの平均所得金額は334.9万円で、所得種類別に見ると、公的年金・恩給が204.5万円と所得全体の中で61.1%で最も多く、次いで稼働所得が85.1万円、25.4%となっている。
この他財産所得や年金以外の社会保障給付金等で賄われている。この状況を見ると、公的年金が老後の所得保障の中核をなしていることが分かる。
◇次に公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見たのが図のようになっている。
これを10年前と比較してみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯は平成21年調査では全体の64%を占めていたが、この10年間に51%まで低下してきていることがわかる。
これは働く高齢者が最近増えていることを如実に物語っている。
特に最近は、人生100年時代を迎え個人にとっては老後の期間が長くなることが見込まれている一方、社会的には人口減少社会で、労働力人口が減少していく現実があり、この情勢に対応するためには、健康で働く意思と能力を持っている高齢者の社会参加が必要であり、高齢者を社会の支え手として活躍出来る社会環境を国をはじめ、地方も企業も整備することが望まれる所以である。
【表】公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の中で公的年金・恩給が総収入に占める割合
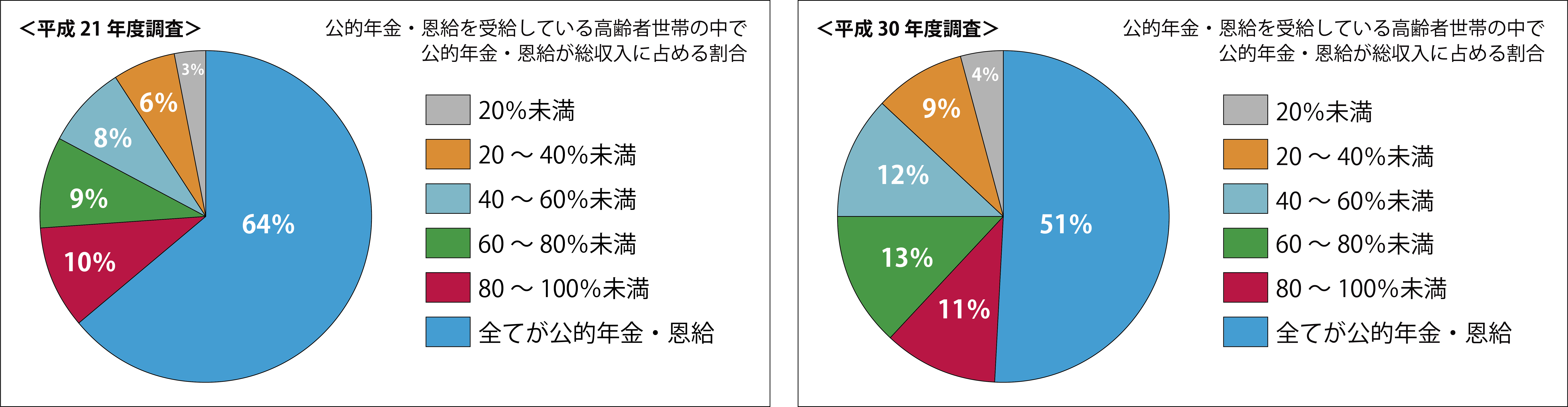
※厚生労働省は、保健、医療、福祉、年金や所得等の国民生活の基本となる項目を調査し、厚生労働行政の企画や運営に当たる国民生活基礎調査を毎年実施している。その中から老後の年金について、10年前と比較した表である。
今後の公的年金制度改正の方向性
二回に亘り公的年金制度のこれまでの発展段階と現状について、見てきたが、今回は今後ますます高齢化が進み、年金受給者が増加する一方で、それを支える現役世代が減少していくことが見込まれており、年金制度がどうなっていくのか不安があるとの声があるので、今後の公的年金制度の方向性についてみる。
政府は今後の高齢社会に対応する基本的課題、総合的な高齢者対策の指針として、平成30年2月に⎾高齢社会対策大綱⏌を閣議決定している。そこで、今回は高齢社会対策大綱に見る公的年金制度の在り方についてみてみよう。
◇持続可能で安定的な公的年金制度の運営
21世紀における、年金制度の課題は、長寿化によって増大する給付費用にたいし、支え手の負担可能な範囲に負担を留める中で給付を削減し、しかも年金制度として必要な給付を確保することである。このような観点にたって平成16年改正は行われた。すなわち、現役世代に対しては、上限を決めた保険料の引き上げを行うと共に、年金受給者については、マクロ経済スライドによる年金の給付水準の自動調整を導入する。更に基礎年金の国庫負担割合を三分の一から二分の一へ引き上げる等の改正がおこなわれた。今後は、これら決められた収入の範囲内で、年金給付水準を確保する長期的な視野に立って年金制度を運営することとなった。
◇高齢期における職業生活の多様性に対応した年金制度の構築
一方、高齢期における働き方は個々人の健康状態や短時間労働など極めて多様化している。また、現在は年金の受給開始時期は60歳から70歳までの間で個人が自由に選べる仕組みになっている。今後は70歳以降の受給開始を選択可能にするなど、年金受給者にとって柔軟で使いやすい制度に向けた検討が行われることになる。この他、現在の在職老齢年金制度についても、高齢期における多様な就業と引退へ対応する観点から、在り方を検討することとされている。
◇働き方に中立的な年金制度の構築
多様な働き方が定着する中で働き易い環境を整えるとともに、短時間労働者に対する年金等の保障を厚くする観点から企業への影響も勘案しつつ、被用者保険の適用拡大に向けた検討が行われることとなっている。
◇終わりに
これまで見てきたように公的年金制度は、老後における所得保障の中核を担う存在である。誰でも歳をとれば若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下する。しかもこれからは長寿化により老後の期間が長くなる。一方、家族構成は核家族化の進行で子どもからの仕送りなど私的扶養が困難な状況にある。定期的に確実に支払いが行われ、終身に亘って受けられる公的年金制度の重要性はますます高まっていく。現在、公的年金は高齢者世帯の所得の約7割を占めると共に、国民の四人に一人が年金受給者となっている。まさに国民生活に不可欠な役割を果たしている。このように見てくると年金制度は長期に亘る制度であり、その時々の社会・経済・人口構造の変化等にも柔軟に対応し、今後も発展していくことが期待されている。
